大阪環状線は、大阪市中心部を一周するJR西日本の鉄道路線です。その歴史は、既存の路線をつなぎ合わせて環状運転を実現した点が特徴です。
黎明期:環状線ができるまで
- 大阪鉄道と城東線
- 1895年(明治28年):私鉄の大阪鉄道が、天王寺~玉造間を開業。その後、大阪駅まで延伸しました。
- 1900年(明治33年):大阪鉄道が関西鉄道に合併され、その後、国有化により「城東線」となります。これが、現在の大阪環状線の東半分を形成しました。
- 西成鉄道と西成線
- 1898年(明治31年):私鉄の西成鉄道が、大阪~安治川口間を開業。これが、現在の大阪環状線の北西部と桜島線の区間にあたります。
- 1906年(明治39年):国有化され、「西成線」となります。
環状線の誕生
- 戦後の環状線建設
- 戦後、大阪市の都市計画の一環として、環状線の建設が具体的に進められました。
- 安治川を渡る橋の建設など、多くの課題を乗り越え、工事が進められました。
- 1961年(昭和36年)4月25日:西九条~天王寺間を結ぶ新線が開業しました。これにより、既存の城東線、西成線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。しかし、この時点ではまだ高架工事が未完成で、一部区間で乗り換えが必要でした。
環状運転の開始と発展
- 1964年(昭和39年)3月22日:西九条駅の高架工事が完成し、名実ともに環状運転がスタートしました。オレンジ色の電車が大阪市内を一周する現在の運行形態が確立されました。
- 1973年(昭和48年):関西本線(大和路線)からの快速電車が、大阪環状線に直通運転を開始しました。
- 1983年(昭和58年):大阪城公園駅が開業。
- 1989年(平成元年):阪和線から天王寺駅を経由し、大阪環状線に直通する特急「くろしお」の運行が始まりました。
- 1994年(平成6年):関西国際空港の開港に伴い、関空特急「はるか」や関空快速が大阪環状線に乗り入れるようになりました。
近年の変化
- 2013年(平成25年):「大阪環状線改造プロジェクト」が発表され、駅のリニューアルや新型車両(323系)の導入が進められました。
- 2016年(平成28年):新型車両323系が営業運転を開始し、従来の103系や201系が順次引退しました。
- 2023年(令和5年):特急「はるか」「くろしお」が大阪駅地下ホーム発着となり、大阪環状線内での運行形態が変化しました。
大阪環状線は、大阪の都市交通の根幹をなす路線として、開業以来、運行形態や車両の近代化を重ねて現在に至ります。
O 01 天王寺
O 02 寺田町
O 03 桃谷
O 04 鶴橋
O 05 玉造
O 06 森ノ宮
O 07 大阪城公園
O 08 京橋
O 09 桜ノ宮
O 10 天満
O 11 大阪
O 12 福島
O 13 野田
O 14 西九条
O 15 弁天町
O 16 大正
O 17 芦原橋
O 18 今宮
O 19 新今宮
O 01 天王寺



R大阪環状線の天王寺駅は、大阪環状線の南の拠点であり、多くの路線が乗り入れるターミナル駅です。その歴史は、現在の大阪環状線が成立する以前にまで遡ります。
黎明期:ターミナル駅としての出発
- 1889年(明治22年)5月14日:私鉄の大阪鉄道が、湊町(現在のJR難波)~柏原間で開業した際、その途中の駅として「天王寺」駅が開業しました。
- 1895年(明治28年)5月28日:大阪鉄道が天王寺~玉造間を延伸開業。これにより、現在の大阪環状線の東半分が形成され、天王寺駅はその起点の一つとなりました。
環状線への編入と発展
- 1900年(明治33年):大阪鉄道が関西鉄道に合併され、その後国有化されます。この路線は「城東線」となります。
- 1929年(昭和4年):阪和電気鉄道(現在のJR阪和線)が開業し、天王寺駅に乗り入れを開始しました。これにより、天王寺駅は南大阪方面への玄関口としての役割を強めます。
- 1961年(昭和36年)4月25日:西九条~天王寺間の新線が開業し、西成線(現在の大阪環状線西半分)と城東線が結ばれ、「大阪環状線」が成立しました。天王寺駅は、その環状運転の拠点駅の一つとなりました。
駅構造の近代化と多機能化
- 1964年(昭和39年):大阪環状線の環状運転が本格的にスタートし、天王寺駅は環状線と、関西本線(大和路線)、阪和線の乗り換えターミナルとしてさらに重要性を増しました。
- 1989年(平成元年):阪和線から大阪環状線に直通する特急「くろしお」の運行が始まり、天王寺駅は特急列車の停車駅となりました。
- 1994年(平成6年):関西国際空港の開港に伴い、関空特急「はるか」や関空快速が乗り入れるようになり、空港アクセス駅としても重要な役割を担うようになりました。
近年の動き
- 2014年(平成26年):「天王寺駅リニューアル」プロジェクトが始動し、駅構内の商業施設「天王寺ミオ」の改装や、駅施設の美装化が進められました。
- 2023年(令和5年):特急「はるか」「くろしお」が大阪駅地下ホーム発着となり、天王寺駅での特急列車の発着ホームが変更されました。
天王寺駅は、大阪の南の玄関口として、また大阪環状線の主要駅として、鉄道の発展とともにその姿を変え、現在に至っています。
O 02 寺田町



JR大阪環状線 寺田町駅は、天王寺駅と桃谷駅の間に位置する駅です。天王寺駅のすぐ隣にありながら、駅周辺は住宅街が広がっています。
開業から環状線へ
- 1932年(昭和7年)7月16日: 当時の城東線(現在の大阪環状線東半分)の駅として開業しました。この駅は、天王寺駅と桃谷駅の駅間距離が長かったため、その中間に位置する駅として新設されました。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 大阪環状線が成立し、寺田町駅はその東半分の駅として組み込まれました。
その後の動き
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の環状運転が本格的に開始され、寺田町駅は環状線の電車が停車する駅となりました。
- 1990年代: 駅の高架化工事が進められ、駅周辺の利便性が向上しました。
- 2016年(平成28年): 大阪環状線に新型車両323系が導入され、寺田町駅でも順次323系による運転が開始されました。
- 2018年(平成30年): 駅舎がリニューアルされ、モダンな外観となりました。
寺田町駅は、駅名の由来にもなっている寺田町(現在の大阪市天王寺区)に位置し、駅のすぐ南側には寺院が多数点在する静かな住宅街が広がっています。
O 03 桃谷



JR大阪環状線 桃谷駅は、大阪市天王寺区に位置し、駅周辺は商店街や住宅地が広がる活気のあるエリアです。
開業と駅名
桃谷駅は、もともと「桃山」という地名から名付けられました。現在の駅名は、駅周辺の桃の木が多かったことに由来しています。
- 1932年(昭和7年)7月16日:城東線(現在の大阪環状線東半分)の駅として開業しました。
環状線への編入
戦後、大阪市内の鉄道網整備が進められ、既存の路線をつなぎ合わせて環状運転が実現しました。
- 1961年(昭和36年)4月25日:大阪環状線が成立し、桃谷駅はその東半分の駅として組み込まれました。
- 1964年(昭和39年)3月22日:環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
その後の変化
- 2006年(平成18年):駅舎の老朽化に伴い、現在の橋上駅舎に改築されました。この改築により、エレベーターやエスカレーターが設置され、バリアフリー化が進みました。
- 2016年(平成28年):「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入され、桃谷駅にも順次新車両が乗り入れるようになりました。
O 04 鶴橋



JR大阪環状線 鶴橋駅は、大阪市生野区に位置し、近畿日本鉄道(近鉄)との連絡駅として、また駅周辺の焼肉店やコリアンタウンで知られています。その歴史は、大阪鉄道の時代にまで遡ります。
開業と駅の発展
- 1895年(明治28年)5月28日: 私鉄の大阪鉄道が天王寺〜玉造間を開業した際に、「鶴橋」駅として開業しました。これが現在の大阪環状線東半分の基礎となりました。
- 1900年(明治33年): 大阪鉄道が関西鉄道に合併され、その後国有化され、「城東線」となります。
- 1914年(大正3年)4月30日: 参宮急行電鉄(現在の近鉄大阪線)が鶴橋駅に乗り入れを開始しました。これにより、鶴橋駅はJRと近鉄の乗り換え駅としての役割を持つようになりました。
高架化と環状線への編入
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の城東線や西成線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。鶴橋駅は、その環状線の一部となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。この高架化により、駅周辺の交通渋滞が緩和されました。
近年の変化
- 1990年(平成2年): 駅舎の改良工事が行われ、駅施設が近代化されました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入され、鶴橋駅にも順次新車両が乗り入れるようになりました。
- 2018年(平成30年): 近鉄線との乗り換えの利便性を向上させるための改良工事が行われました。
鶴橋駅は、JRと近鉄が交わる交通の要衝であり、特に駅の高架下にある商店街は、多くの人々で賑わっています。
O 05 玉造

JR大阪環状線 玉造駅は、大阪市東成区と中央区の境界に位置する駅で、大阪環状線の東半分を形成する区間の歴史を物語る駅の一つです。
開業と環状線への編入
- 1895年(明治28年)5月28日: 私鉄の大阪鉄道が、天王寺〜玉造間を開業した際の終着駅として開業しました。これが現在の大阪環状線東半分の基礎となりました。
- 1900年(明治33年): 大阪鉄道が関西鉄道に合併され、その後国有化されます。この路線は「城東線」となります。
高架化と駅の近代化
- 1933年(昭和8年): 玉造駅を含む城東線の高架化が完成しました。これにより、駅周辺の交通渋滞が緩和されました。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の城東線や西成線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。玉造駅は、その環状線の一部となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
- 2014年(平成26年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、駅舎のリニューアル工事が実施されました。
玉造駅は、駅名の由来にもなっている「玉造」という歴史的な地名に位置し、駅のすぐ南側には地下鉄長堀鶴見緑地線の玉造駅があり、乗り換えが可能です。
O 06 森ノ宮



R大阪環状線 森ノ宮駅は、大阪市中央区と東成区の境界に位置し、大阪城公園の東側に広がる駅です。
開業と環状線への編入
- 1932年(昭和7年)3月21日: 城東線(現在の大阪環状線東半分)の駅として開業しました。駅の建設は、当時近隣にあった陸軍の施設や、大阪市営地下鉄(現在の大阪メトロ)の森之宮検車場(車両基地)の建設に関連していたといわれています。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の城東線や西成線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。森ノ宮駅は、その環状線の一部となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
その後の変化
- 1967年(昭和42年):駅の南側にあった貨物取扱施設が廃止されました。
- 1990年(平成2年): 花博(国際花と緑の博覧会)の開催に伴い、JR東西線が京橋駅から森ノ宮駅まで延伸され、地下鉄との乗り換え駅となりました。
- 1997年(平成9年): 大阪市営地下鉄中央線(現在の大阪メトロ中央線)と長堀鶴見緑地線が開通し、森ノ宮駅は両線の乗り換え駅としてさらに重要性を増しました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
森ノ宮駅は、JR大阪環状線と大阪メトロ中央線・長堀鶴見緑地線が交差する交通の要衝であり、また、大阪城公園や大阪歴史博物館への最寄り駅としても知られています。
O 07 大阪城公園


JR大阪環状線 大阪城公園駅は、大阪城公園の東側に位置する、観光の拠点となる駅です。その歴史は、大阪環状線の駅の中でも比較的新しい駅です。
駅の誕生
- 1983年(昭和58年)10月1日: 国鉄(当時)城東線の駅として開業しました。大阪城公園を訪れる観光客の利便性向上を目的に新設されました。
民営化とその後
- 1987年(昭和62年)4月1日: 国鉄の分割民営化に伴い、JR西日本の駅となりました。
- 1990年(平成2年): 「国際花と緑の博覧会(花博)」の開催に伴い、多くの来場者で賑わいました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
大阪城公園駅は、開業以来、大阪城や大阪城ホール、大阪城公園を訪れる人々にとって重要なアクセスポイントとなっています。駅舎は大阪城をイメージしたデザインとなっており、駅のホームからは大阪城天守閣の一部を望むことができます。
O 08 京橋



JR大阪環状線 京橋駅は、大阪市城東区に位置する主要なターミナル駅です。大阪環状線だけでなく、JR東西線、京阪本線、大阪メトロ長堀鶴見緑地線が乗り入れる交通の要衝として、その歴史を築いてきました。
開業と路線の発展
- 1895年(明治28年)10月17日: 私鉄の浪速鉄道が片町〜四条畷間で開業した際に、「片町」駅として開業しました。これが現在のJR学研都市線(片町線)の基礎です。
- 1896年(明治29年): 浪速鉄道が延伸し、京橋駅が開業しました。当時は、京橋は大阪市街地の東端に位置していました。
- 1907年(明治40年): 浪速鉄道が国有化され、国鉄の駅となります。
鉄道の結節点へ
- 1910年(明治43年)4月15日: 京阪電気鉄道の京橋駅が開業しました。これにより、京橋は国鉄と京阪の乗り換え駅となります。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 大阪環状線が成立し、京橋駅は環状線と片町線(現在の学研都市線)の接続駅となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の環状運転が本格的に開始され、京橋駅は大阪都心部の主要駅としての地位を確立しました。
- 1997年(平成9年)3月8日: JR東西線が開業し、京橋駅は学研都市線とJR東西線の直通運転の起点となりました。また、大阪メトロ長堀鶴見緑地線も乗り入れを開始し、さらなる交通の利便性が向上しました。
近年の変化
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
- 2019年(平成31年): JR京橋駅の駅ビルがリニューアルされ、駅ナカ商業施設「エキマルシェ京橋」が開業しました。
京橋駅は、JRだけでも大阪環状線、JR東西線、学研都市線の3路線が乗り入れる複雑な構造を持つ駅であり、大阪東部の主要なターミナル駅として現在も多くの利用客で賑わっています。
O 09 桜ノ宮


JR大阪環状線 桜ノ宮駅は、大阪市都島区に位置し、大川沿いの桜並木が美しいことで知られています。その歴史は古く、大阪環状線の前身である城東線の時代にまで遡ります。
開業と駅名
- 1895年(明治28年)10月17日: 私鉄の大阪鉄道の駅として開業しました。当時は、現在の大阪環状線の東半分にあたる区間を運行していました。駅名は、駅の近くにある「桜之宮公園」に由来しています。
- 1900年(明治33年): 大阪鉄道が関西鉄道に合併された後、国有化され「城東線」となります。この時点でも、桜ノ宮駅は主要な駅の一つでした。
高架化と環状線への編入
- 1933年(昭和8年): 玉造駅から桜ノ宮駅を含む城東線の高架化が完成しました。これにより、駅周辺の交通がスムーズになりました。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の城東線や西成線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。桜ノ宮駅は、その環状線の一部となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
その後の変化
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入され、順次従来の車両と置き換えられました。
- 2018年(平成30年): 駅舎がリニューアルされ、モダンなデザインになりました。また、駅周辺の景観と調和するよう、桜のイラストなどがデザインに取り入れられました。
桜ノ宮駅は、大川沿いに広がる桜之宮公園へのアクセス駅として、特に春には多くの花見客で賑わいます。
O 10 天満


JR大阪環状線 天満駅は、大阪市北区に位置し、日本一長い商店街として知られる天神橋筋商店街の最寄り駅です。その歴史は、大阪環状線の中でも特に古く、大阪市内の鉄道網の黎明期から存在しています。
開業と駅の発展
- 1895年(明治28年)10月17日: 私鉄の大阪鉄道の駅として開業しました。当時は、現在の大阪環状線の東半分にあたる区間を運行していました。駅名は、近くにある大阪天満宮に由来しています。
- 1900年(明治33年): 大阪鉄道が関西鉄道に合併された後、国有化され「城東線」となります。この時点で、天満駅は城東線の主要駅の一つでした。
高架化と環状線への編入
- 1933年(昭和8年): 玉造駅から天満駅を含む城東線の高架化が完成しました。これにより、地上を走っていた線路がなくなり、駅周辺の交通渋滞が緩和されました。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の城東線や西成線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。天満駅は、その環状線の一部となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
近年の変化
- 1997年(平成9年): 駅舎が改装され、駅の利便性が向上しました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入され、順次従来の車両と置き換えられました。
天満駅は、駅のすぐ西側に天神橋筋商店街が広がり、活気のある商店街と下町情緒が魅力の駅です。
O 11 大阪

JR大阪駅は、大阪市北区に位置し、JR各社の主要路線が集まる西日本最大のターミナル駅です。大阪環状線の駅としては起終点の役割も果たしており、その歴史は日本の鉄道の黎明期にまで遡ります。
開業と路線の発展
- 1874年(明治7年)5月11日: 日本で2番目の鉄道として、大阪〜神戸間に鉄道が開業した際の終着駅として「大阪」駅が開業しました。
- 1876年(明治9年): 京都まで延伸され、大阪駅は東西を結ぶ重要な結節点となります。
- 1895年(明治28年): 私鉄の大阪鉄道(現在の関西本線、大阪環状線の一部)が大阪駅に乗り入れを開始しました。これにより、大阪駅は名実ともに大阪の玄関口となりました。
環状線への編入と駅の巨大化
- 1900年(明治33年): 大阪鉄道が国有化され、大阪駅は国鉄の駅となります。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 大阪環状線が成立し、大阪駅は環状線の駅として組み込まれました。この時、西成線(現在の大阪環状線の一部)と城東線(現在の大阪環状線の一部)が結ばれ、環状運転が本格的に始まりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、環状運転が定着しました。
- 1979年(昭和54年): 貨物駅が廃止され、その跡地は再開発され、現在の「グランフロント大阪」などへと生まれ変わります。
- 1983年(昭和58年): 駅ビル「アクティ大阪」(現:サウスゲートビルディング)が開業しました。
近年の大規模な再開発
- 2011年(平成23年): 「大阪ステーションシティ」として、大規模な駅改良工事が完了しました。ノースゲートビルディングとサウスゲートビルディングが全面リニューアルされ、駅上空に巨大なドーム屋根「時空(とき)の広場」が設置されました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
- 2023年(令和5年): JR大阪駅(うめきたエリア)の地下ホームが開業しました。これにより、特急「はるか」「くろしお」が大阪駅に乗り入れるようになり、利便性がさらに向上しました。
大阪駅は、その歴史を通じて、大阪の発展とともに常に進化し続けてきました。現在も、西日本の交通網の心臓部として重要な役割を担っています。
O 12 福島


JR大阪環状線 福島駅は、大阪市福島区に位置し、梅田や大阪の都心部からほど近い場所にあります。その歴史は、現在の大阪環状線の西半分を形成した西成線の時代にまで遡ります。
開業と環状線への編入
- 1898年(明治31年)4月1日: 私鉄の西成鉄道が、大阪〜安治川口間で開業した際に、「福島」駅として開業しました。これが現在の大阪環状線の西半分と桜島線の区間にあたります。
- 1906年(明治39年): 西成鉄道が国有化され、「西成線」となります。
- 1943年(昭和18年)4月1日: 駅舎が移転されました。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の西成線や城東線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。福島駅は、その環状線の一部となりました。
駅の近代化と周辺の発展
- 1987年(昭和62年): 国鉄の分割民営化に伴い、JR西日本の駅となりました。
- 1990年(平成2年): 駅周辺の高架下に飲食店や商業施設がオープンし、活気のあるエリアとなりました。
- 1997年(平成9年)3月8日: JR東西線が開業し、新福島駅が開業しました。これにより、JR環状線の福島駅とJR東西線の新福島駅、そして阪神本線の福島駅が近接し、乗り換えが可能となりました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
福島駅は、JR大阪駅から一駅という都心に近く、また、JR東西線や阪神電車との乗り換えも可能であり、利便性の高い駅として多くの人に利用されています。駅周辺は、近年再開発が進み、高層マンションやオフィスビルが立ち並ぶエリアとなっています。
O 13 野田


JR大阪環状線 野田駅は、大阪市福島区に位置し、阪神本線の野田駅、大阪メトロ千日前線の野田阪神駅と連絡しており、交通の要衝となっています。その歴史は、大阪環状線の西半分を形成した西成線の時代にまで遡ります。
開業と駅名
- 1898年(明治31年)4月1日: 私鉄の西成鉄道が、大阪〜安治川口間で開業した際に、「野田」駅として開業しました。
- 1906年(明治39年): 西成鉄道が国有化され、「西成線」となります。
環状線への編入と駅の改良
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の西成線や城東線と合わせて「大阪環状線」が成立しました。野田駅は、その環状線の一部となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
- 1965年(昭和40年): 駅舎が改築されました。
- 1969年(昭和44年): 阪神電車の野田駅が隣接する場所に高架化されました。
- 1984年(昭和59年): 駅のホームが延長され、8両編成の列車に対応できるようになりました。
近年の変化
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
- 2018年(平成30年): 駅舎のリニューアルが行われ、モダンなデザインになりました。
野田駅は、JR、阪神電車、大阪メトロの3路線が利用できる利便性の高い駅として、現在も多くの利用客で賑わっています。
O 14 西九条



JR大阪環状線 西九条駅は、大阪市此花区に位置する主要な乗り換え駅です。大阪環状線とJRゆめ咲線(桜島線)の分岐点であり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)への玄関口として、また、阪神なんば線との接続駅としても重要な役割を担っています。
黎明期:貨物線としての開通
- 1898年(明治31年)4月1日: 私鉄の西成鉄道が、大阪〜安治川口間で開業した際の駅の一つとして、「西九条」駅が開業しました。この区間は、大阪の港湾部への貨物輸送を主な目的としていました。
- 1906年(明治39年): 西成鉄道が国有化され、「西成線」となります。
環状線への編入
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業しました。これにより、既存の城東線(大阪環状線東半分)と西成線が結ばれ、大阪環状線が成立しました。西九条駅は、この環状線と桜島線(旧・西成線の一部)の分岐点となり、重要な駅となりました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
近年の変化
- 2001年(平成13年)3月31日: ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が開業しました。これに伴い、西九条駅から桜島駅までの路線が「JRゆめ咲線」という愛称で呼ばれるようになり、USJへのアクセス駅として、多くの観光客で賑わうようになりました。
- 2009年(平成21年)3月20日: 阪神なんば線が開業し、阪神西九条駅が開設されました。これにより、大阪環状線の西九条駅と阪神なんば線の駅が接続され、奈良方面や近鉄沿線への乗り換えが便利になりました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
西九条駅は、大阪環状線、JRゆめ咲線、阪神なんば線の3路線が乗り入れる交通の要衝として、現在も重要な役割を担っています。
O 15 弁天町



JR大阪環状線 弁天町駅は、大阪市港区に位置し、大阪環状線の主要駅の一つです。特に、地下鉄中央線との乗り換え駅として重要な役割を担っています。
開業と環状線への編入
- 1961年(昭和36年)4月25日: 国鉄(当時)大阪環状線の全線開通に伴い開業しました。元々は、駅周辺の地名である「市岡」から駅名を付ける案もありましたが、すでに岡山県に市岡駅が存在していたため、近くの町名にちなんで「弁天町」駅と名付けられました。
- 1961年(昭和36年)12月11日: 大阪市高速鉄道4号線(現在のOsaka Metro中央線)が大阪港〜弁天町間で開業し、JR環状線との乗り換え駅となりました。
駅の発展と交通科学博物館
- 1962年(昭和37年)1月21日: 弁天町駅の隣接地に「交通科学博物館」が開館しました。これは、国鉄が開業した鉄道を中心とした交通の博物館で、弁天町駅は博物館の最寄り駅として多くの鉄道ファンや家族連れで賑わいました。
- 1987年(昭和62年)4月1日: 国鉄の分割民営化に伴い、JR西日本の駅となりました。
- 2014年(平成26年)4月6日: 交通科学博物館が閉館し、その機能は京都に新設された「京都鉄道博物館」に移転されました。
近年の大規模な再開発
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
- 2025年(令和7年): 2025年大阪・関西万博の開催に向け、交通科学博物館跡地を活用した大規模な駅改良工事が完了しました。これにより、地下鉄中央線との乗り換えがスムーズに行える新駅舎が整備され、万博来場者や地域住民の利便性が大幅に向上しました。
O 16 大正



JR大阪環状線 大正駅は、大阪市大正区に位置し、駅名の由来にもなっている大正区の玄関口です。沖縄からの移住者が多く、沖縄料理店が点在することでも知られています。
開業と環状線への編入
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の西成線と城東線を結び、大阪環状線が成立した際に開業しました。大正区の区名が駅名に採用されました。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が始まりました。
その後の発展と交通の要衝へ
- 1997年(平成9年)8月29日: 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線(現:Osaka Metro長堀鶴見緑地線)が大正駅まで延伸開業し、JRとの乗り換え駅となりました。これにより、心斎橋や京橋方面へのアクセスが向上しました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
大正駅は、JRと地下鉄が乗り入れる交通の要衝であり、また、京セラドーム大阪の最寄り駅の一つとして、イベント開催時には多くの人々で賑わいます。
O 17 芦原橋


R大阪環状線 芦原橋駅は、大阪市浪速区に位置し、駅名にもなっている「芦原」地区にあります。
開業から環状線へ
- 1900年(明治33年): 現在の大阪環状線の前身である大阪鉄道の駅として、「芦原町」駅が開業しました。
- 1907年(明治40年): 国有化され、国鉄の駅となります。
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の西成線と城東線が結ばれ、「大阪環状線」が成立した際に、「芦原橋」駅に改称されました。これは、駅の近くに架かる芦原橋に由来しています。
駅の近代化と地域との関わり
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始されました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
- 2018年(平成30年): 駅舎がリニューアルされ、モダンなデザインになりました。また、駅周辺の歴史を反映し、太鼓のモニュメントなどが設置されました。
芦原橋駅は、地域に根差した駅であり、駅周辺の太鼓文化や皮革産業の歴史を伝えるイベントなどが開催されています。
O 18 今宮



R大阪環状線 今宮駅は、大阪市浪速区に位置し、関西本線(大和路線)との乗り換え駅です。その歴史は、現在の大阪環状線が成立する前から、重要なターミナル駅として存在していました。
開業と駅の発展
- 1889年(明治22年)5月14日: 私鉄の大阪鉄道が、湊町(現在のJR難波)〜柏原間で開業した際に、「今宮」駅として開業しました。当時は、大阪鉄道の本社も駅構内にありました。
- 1895年(明治28年): 大阪鉄道は天王寺方面へ延伸し、今宮駅は分岐駅として機能しました。
- 1900年(明治33年): 大阪鉄道が国有化され、国鉄の駅となります。
環状線への編入と近代化
- 1961年(昭和36年)4月25日: 西九条〜天王寺間の新線が開業し、既存の西成線や城東線と合わせて大阪環状線が成立しました。今宮駅は、環状線の駅として組み込まれましたが、環状線のホームは関空快速などの一部列車のみが停車するのみでした。
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が始まりました。
- 1997年(平成9年)3月8日: 新大阪駅とJR難波駅を結ぶなにわ筋線の建設計画に伴い、JR難波方面から環状線へ直通する列車に対応するためのホーム改良工事が行われました。
- 2001年(平成13年)3月3日: 新しい橋上駅舎が開業し、環状線のホームと大和路線のホームが一体化しました。これにより、乗り換えが非常に便利になりました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
今宮駅は、JR難波駅に近いため、大阪市内での移動において重要な役割を担っています。
O 19 新今宮



JR大阪環状線 新今宮駅は、大阪市浪速区に位置し、大阪の観光地「新世界」や「通天閣」への玄関口です。南海電気鉄道や阪堺電気軌道との乗り換え駅でもあり、交通の要衝として重要な役割を担っています。
開業から環状線へ
- 1964年(昭和39年)3月22日: 大阪環状線の全線高架化が完了し、本格的な環状運転が開始された際に、その東側の区間を走る城東線上に「新今宮」駅として開業しました。
- 1966年(昭和41年)12月1日: 駅舎が完成し、営業を開始しました。
- 1968年(昭和43年): 難波方面から地下鉄御堂筋線への乗り換えが不便だったため、新今宮駅が開業しました。また、駅の近くには南海電鉄の駅がありましたが、乗り換えの利便性を考慮して、両駅を接続する連絡通路が整備されました。
その後の発展と近代化
- 1987年(昭和62年)4月1日: 国鉄の分割民営化に伴い、JR西日本の駅となりました。
- 1990年(平成2年): 駅の改良工事が行われ、駅舎がリニューアルされました。
- 1993年(平成5年): 新今宮駅の近くに「スパワールド」が開業し、駅の利用客が増加しました。
- 2016年(平成28年): 「大阪環状線改造プロジェクト」の一環として、新型車両323系が導入されました。
新今宮駅は、大阪観光の拠点として、また関西国際空港へのアクセス駅としても重要な役割を担っており、南海電鉄や阪堺電気軌道との乗り換え客で常に賑わっています。


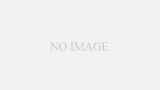
コメント